組織開発と心理的安全性:なぜ “安心できる職場” が成長を加速させるのか?

「もっと意見を出してほしいのに、社員が黙ってしまう」
「新しい取り組みを提案しても、誰も反応しない」
「指示待ちが多く、自分で考えて動かない」
こうした状況の背景には、単に “やる気の欠如” ではなく、心理的安全性の欠如が潜んでいることが多いのです。
そして、この心理的安全性を高めることこそが、組織開発の中核にあるのです。
心理的安全性とは?
心理的安全性とは、ハーバード大学のエイミー・エドモントソン教授が提唱した概念で、
「この職場では、ミスや意見を言っても拒絶や攻撃をされないと信じられる状態」
を意味します。
要するに、社員が「安心して話せる」「行動できる」と感じることができるかどうか、です。
組織開発との関係
組織開発は、人と組織の関係性を改善し、学習と成長を促す営みです。
その土台になるのが心理的安全性。
心理的安全性が低い組織では、
-
意見が出ない
-
問題が隠される
-
改善が進まない
-
上からの指示待ちになる
逆に心理的安全性が高い組織では、
-
会議でアイデアや懸念が出る
-
失敗から学びが共有される
-
自発的な改善が始まる
-
上司と部下の関係が信頼で結ばれる
つまり、心理的安全性の有無が、組織開発の成功と失敗を分ける分水嶺になるのです。
心理的安全性を高める3つの実践ポイント
① 上司が「まず聴く」姿勢を見せる
-
「そんなの無理」と否定する前に、「なるほど、どういうこと?」と聴く
-
部下の発言を途中で遮らない
→ 「言っても大丈夫」と思える体験が積み重なっていくことが重要です。
② 小さな意見を拾って認める
-
会議での小さな指摘にも「いい気づきだね」と反応
-
現場での改善を「ありがとう、助かった」と言葉にする
→ 承認が続くと、社員は「また言ってみよう」と思えるようになります。
③ 失敗を “学び” として扱う
-
失敗した社員を責めるのではなく、「この経験から次に活かせることは?」と問いかける
-
組織全体で共有して再発防止・改善につなげる
→ 「失敗しても終わりではない」と思えることで挑戦が増えていきます。
実際の現場事例
ある社員10名の町工場では、最初「提案を出せ」と言っても誰も手を挙げませんでした。
しかし、社長がまず「小さな気づきでもOK」「否定はしない」と宣言。
さらに「教えてくれてありがとう」を口ぐせにしたところ、1ヶ月後には若手から改善アイデアが出るように。
半年後には、「もっとこうした方が効率的では?」という声が自然に飛び交うようになり、現場の改善スピードが2倍に向上しました。
まとめ:“安心できる土台” の上に組織開発は成り立つ
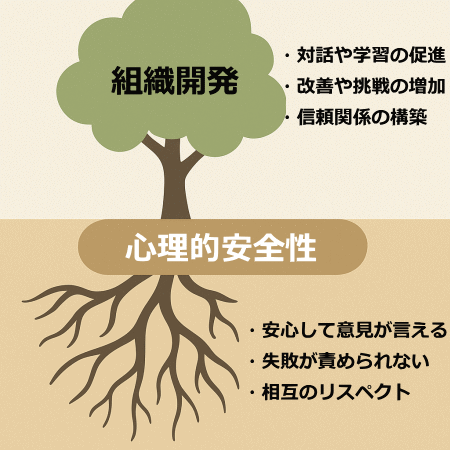
-
組織開発は「制度改革」や「仕組みづくり」だけでは機能しない
-
心理的安全性という“土台”があって初めて、対話や学びが回り始める
-
その土台を耕すのは、社長やリーダーの日々のふるまい
小さな「聴く」「認める」「学び合う」から始めてみませんか?

